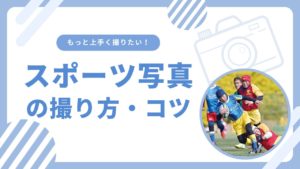先日、久しぶりに大学の食堂で昼食を食べた時のこと。食堂では感染症対策のため席と席の間にアクリル板が設置されており、前の人の表情が鮮明に見えずとても違和感がありました。未だに、きちんと顔を見て、会話をして、そして同じお皿のものを取り分けたりしながら食事をすることを控えなくてはならない状況ですが、この状態が続くと私たちはこれからどうなっていくのだろう……と不安を覚え、考えてみました。
最近本で学んだことです。人間の社会性は、食物を運び、仲間と一緒に安全な場所で食べる「共食」から始まったそうです。野生動物で、大人同士が食べ物を分け合う行為をする動物はほとんどいません。一緒に食べる仲間への信頼と期待が人間の信頼関係の最初の構築と言われています。そして、人と楽しく食卓を囲めるのが人間の証であり、他の動物にはない「いつ、どこで、何を、誰と、どのように」食べるかを私たちは1日の中で何度も課題にしています。では、今の状況が続くと私たちはこの先どうなってしまうのでしょう?もしかして、信頼関係や社会性がなくなり、ある意味野生動物化してしまうのでしょうか……?
状況を急に変えることはできません。では今できることはどんなことか。思いついたことを書いてみます。一緒に食べなくても、食べ物をお裾分けしたり、旅のお土産をあげたり……これは素敵な文化ですよね。今は、SNSでおすすめの料理やレシピを発信することもできます。それらを試すことはまさに信頼と期待の証です。そんな風に考えると、例え一人だとしても「よかったら試してください」と言えるよう自分の食生活をまず大切にするということがやっぱり重要なのかなぁとも思えてきます。
参考:「スマホを捨てたい子どもたち」山極寿ー(ポプラ新書)
武田 哲子(たけだ さとこ)
びわこ成蹊スポーツ大学准教授 / 管理栄養士
競技力向上のための栄養に関する研究をはじめ、自立した食生活を実践するための指導など、運動と栄養を切り口にしたスポーツ選手の育成、サポートを行う。日本セーリング連盟管理栄養士。