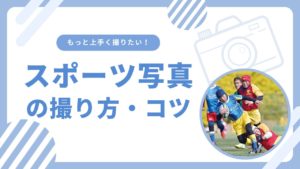最近、身近なところで長期にわたる食育の成果が発揮された場面を目の当たりにしました。
私の父(70代)は子どもの頃から現在に至るまで、自炊が必要な環境で生活したことがない人でした。私の子どもの頃の記憶では、母が外出して夕食の準備がないときは外食できる、もしくはステーキとか焼肉など、簡単だけど子どもにとっては嬉しい夕食の時間でした。「父は料理ができない」と思っていました。
最近母が長期間入院することになり、心配して実家に駆けつけたところ、驚くことに、父は3食完璧な食事を作り、それどころか庭で採れた果物をジャムにしたり、漬物を漬けたり……と母がしていたことと全く同じことをしていたのです。料理ができなかったという事実はその通りなのですが、父には「食事をおろそかにしない」という意識が刻み込まれていたようで、一人になってもインターネットを駆使し、きちんと食事をすることを辞めませんでした。
食育とは、『様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるもの』(食育基本法)と掲げられ、特に子どもの頃にこういった能力を身に付けさせることが重要だと考えられています。私が見た光景はまさに、祖母や母が長年に渡って父に対して積み重ねた食育の成果でした。
食べ方は生き方、食べることを大切にできる人は他人や自分を大切にできる。
ひょっとしたら、子どもの頃の外食やステーキは、父が料理できないという理由ではなく、私たちを喜ばせる食事の仕方を父なりに選択してくれていたのかも……。父の姿を見て、一番大切なことは食事を大切にすること、食事を通して自分や他人を大切にすること。これこそ食育で伝えるべきことなのだと改めて感じました。
武田 哲子(たけだ さとこ)
びわこ成蹊スポーツ大学准教授 / 管理栄養士
競技力向上のための栄養に関する研究をはじめ、自立した食生活を実践するための指導など、運動と栄養を切り口にしたスポーツ選手の育成、サポートを行う。日本セーリング連盟管理栄養士。